1年間の「火の用心」へ

大崎市消防団の出初め式は11日、市民会館であり、市内7支団57分団、女性防火クラブの代表者ら約400人がことし1年間の「火の用心」と防災活動に向けて士気を高めた。新春の恒例行事で、団員たちは伝統の法被姿で参加。伊藤康志市長は「仕事に従事しながらも、市民の生命と財産を災害から守るため昼夜問わず献身的に活躍いただいている。崇高な精神、強い責任感に対し深く敬意と感謝を申し上げる」と告示し、内田博美団長は訓辞で「消防力強化に努め、市民皆さんから信頼される消防団として精進する心構えだ。団員は引き続き秩序、精神、技術を磨いて尽力を」と力を込めた。引き続き古川支団の出初め式も実施。終了後には駐車場で3分団の消防ポンプ車が一斉放水し、真っ青な空に水のアーチを描いた。
1年の無病息災願う

正月飾りや古神札をたき上げて御神火にあたり、1年の無病息災や家内安全などを願う小正月行事「どんと祭」が13日、大崎地方の一部で行われた。裸参りが再開した地域もあり、にぎわいを見せた。実施日を14日夜としているところがほとんどだが、地域によっては15、16日としているところもある。大崎市鹿島台広長の鹿島台神社(岡田英彌宮司)は13日正午から実施。3年前までは14日夜に行っていたが、遠方の臨時駐車場から夜間に徒歩で来社してもらうのは危険を伴うため明るい時間帯に家族連れで訪れてもらおうと、14日に近い休日の日中に移した。祝日のこの日、家族連れが次々訪れた。燃え盛る御神火に正月飾りを投げ入れて暖を取り、家族の平穏や健康を願った。
同市田尻地域では13日、まちづくり委員会や有志団体でつくる実行委員会(伊藤重義会長)が運営を担った。田尻総合体育館グラウンドにうずたかく積まれた札や飾りに火がともされ、燃え上がった。裸参りが5年ぶりに復活。腰にさらしを巻いた有志6人が、神に息をかけないための「含み紙」を口にくわえ、沼部公民館から会場まで20分近くかけて練り歩き、会場では拍手で迎えられた。
流域治水の推進確認
鶴田川沿岸土地改良区(大崎市鹿島台、千葉榮理事長)は10日、「川の流れに感謝のつどい」と題した集まりを地元の鹿島台志田谷地防災センターで開いた。吉田川や鶴田川の沿川住民ら約70人が、国や県による河川改修の進捗状況に触れたほか、官民挙げて流域治水に引き続き取り組むことを確かめた。北上川下流河川事務所と県の担当者が、来年度中の完工を目指して進めている河道掘削のほか、堆積土砂撤去や堤防補強、排水機場機能強化などの進行具合を報告。同事務所の間山隆之副所長は「流域治水に地元住民が主体的に参画していて『吉田川・高城川モデル』として全国から注目され、視察も相次いでいる」と述べた。
鳴子~新庄4往復に増便
JR東日本は14日、大雨の影響で運行を見合わせている陸羽東線の鳴子温泉~新庄(山形県)間で昨年8月23日から実施している代行バスのダイヤを改正した。1日3往復だった鳴子温泉~新庄間を4往復に増やした。新ダイヤでは、上りが午前6時35分、10時5分、午後1時半、3時10分にそれぞれ新庄駅を出発し、各駅停車で約1時間50分後に鳴子温泉駅に着く。下りは午前8時55分、午後1時15分、4時10分、5時半にそれぞれ鳴子温泉駅を出て、同じく各駅停車で新庄駅に向かう。
自分のまちの歴史知ろう
大崎市岩出山の城山公園にある蒸気機関車(SL)について学ぶ講話がこのほど、岩出山小(児童数318人)で行われた。3年生45人が保存団体の代表らから話を聞き、古里の歴史に思いをはせていた。総合学習で児童が岩出山について調べた際、「なぜ城山公園にSLがあるのか」と疑問を持ったのがきっかけ。このSLの修繕や保存を担う鉄道文化連結会(大場正明代表理事)に同校から講話を依頼した。機関士に扮した大場代表が講師を務め、昨年10~12月に行ったSLの修繕作業について紹介。城山公園へ運ばれた1973年当時の映像などを通じ、SLの歴史や保存に至った経緯も解説した。SL設置に立ち会った60代男性会員も思い出を語った。
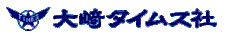
コメントをお書きください